 南海金剛駅の東側から駅を見ると、狭山神社のあたりが小高い山のように見えます。そして調べてみると、中世の頃には狭山神社の境内に河内半田城があった可能性があることがわかりました。
南海金剛駅の東側から駅を見ると、狭山神社のあたりが小高い山のように見えます。そして調べてみると、中世の頃には狭山神社の境内に河内半田城があった可能性があることがわかりました。

(金剛駅側から見た狭山神社の境内。近くに半田城があったと伝わる)
具体的な築城年や城主などは不明ですが、狭山神社の境内の中に土塁(敵の攻撃を守るため盛り土による堤防状の防壁)らしきものが残っているそうです。ただ、「大阪府中世城館事典」の記述では、発掘調査が以前行われたものの城郭遺構と断定できない状況で、場合によっては神社境内の結界の可能性もあるそうです。

南北朝時代に半田城の存在を示す記録があり、それによると北朝側の城として半田城が利用されていたそうです。その根拠として南朝側の高木遠盛や佐備正忠らが1337(建武4・延元2)年に攻めているという記録、さらに明応年間(1492~1501)年に埴田右近という人物が半田城を居城にしていたという記録がありました。
|
|
|

かすかに歴史の記録に残っている河内半田城跡の多くは狭山神社の境内の森の中にあるようですが、実はすぐ北側の坂道は半田城の一部であるという情報を得ました。

 大阪府教育委員会の資料によれば、狭山神社の西側を南北に続いている大阪府道198号「河内長野美原線」で狭山神社の北側から南海金剛駅に抜ける坂道があるのですが、これを「シロノサカ」と資料では呼んでおり、河内半田城に続く道と推定しているとのこと。
大阪府教育委員会の資料によれば、狭山神社の西側を南北に続いている大阪府道198号「河内長野美原線」で狭山神社の北側から南海金剛駅に抜ける坂道があるのですが、これを「シロノサカ」と資料では呼んでおり、河内半田城に続く道と推定しているとのこと。

夜間ですが、「シロノサカ」と呼ばれるこの道は金剛駅に向かう近道なので歩いてみました。南河内における中世城館の調査のうち、「狭山神社遺跡の土塁と半田城」によると、あくまで「可能性のひとつ」として、狭山神社にある二重の土塁を河内半田城の城郭として使用されたと推定しているそうです。
|
|
|

そしてシロノサカを北端として、狭山神社境内の北側を埋蔵文化財包蔵地の「狭山神社遺跡」として認定したうえで、そこから南側部分東西200メートル、南北100メートルのエリアを半田城跡としているそうです。

途中狭山神社の境内につながる藪が見えますが、同時に城跡でもあるわけですね。
|
|
|

これは「シロノサカ」を登り切って振り返ったところです。シロノサカの先に金剛駅があります。金剛駅からさらに東は上り坂となっているのですが、それは羽曳野丘陵があるからで、そこに現代では富田林市内の金剛住宅地があります。そして西側には西除川の流れがあるため標高が低くなっています。

シロノサカの先は下りではなく平坦な道で、金剛駅の近くに行けます。このあたりに昔は谷があったそうですが、今は埋め立てられて車が通れる道になっています。

ということで中世南北朝の時代に北朝側の拠点として南朝側と激突したという伝説の残る河内半田城をご紹介しました。狭山神社の境内に重なっているために、はっきりしない点は多いものの「シロノサカ」と呼ばれる神社北側の急坂にかすかにその痕跡を感じました。
|
|
|

シロノサカ(河内半田城跡)
住所:大阪府大阪狭山市半田1丁目
アクセス:南海金剛駅から徒歩2・3分
この記事を書いた人
奥河内から情報発信
大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。
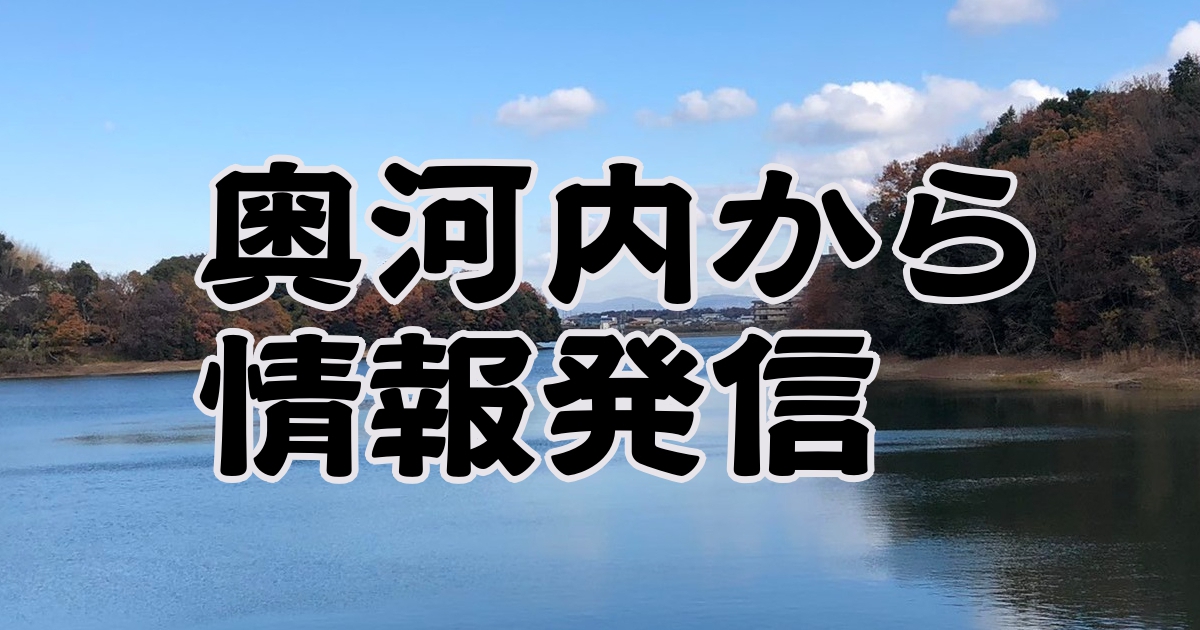



コメント
[…] ただ神社の入り口は反対側なので坂(シロノサカ)を下りる必要があります。 […]